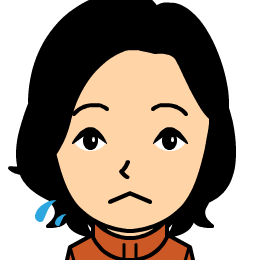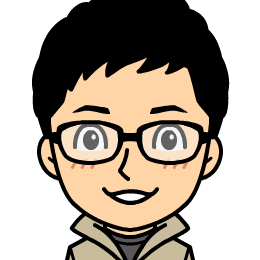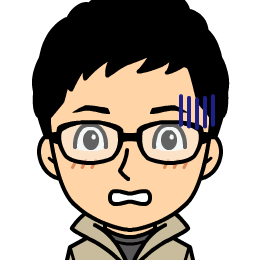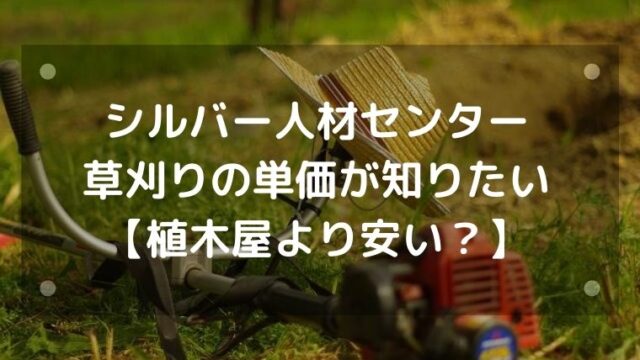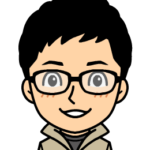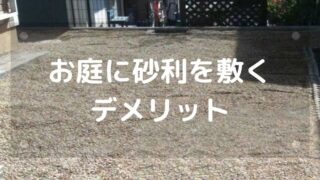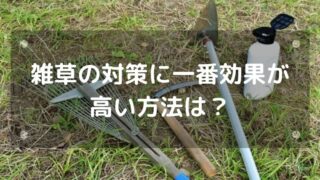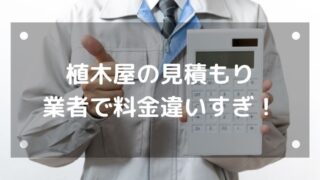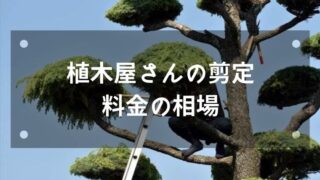こんにちは。
元サラリーマン植木屋として庭木の剪定や草むしりをしつつ、年間500件以上の見積もりに周っていたマキです。
草むしりは何度やってもまた生えてくるのが分かっているので、諦めて放置してしまっているお宅もありますよね。
しかし、草むしりも時期やタイミングを考えてすればかなり簡単になります。
庭や家の周りでも、雑草が次に生えてくるのを抑えてくれることもできるので、草むしりや草取りのタイミングや時期をご紹介しましょう。
草むしりの時期とタイミング

草には多くの種類がありますが、庭などに生える草であればだいたいは一番最初に発芽が始まるのは春の時期で3月頃です。
冬に枯れた雑草が元気よく生えてきますので、3月から草むしりをする時期が始まると言えるでしょう。
芽が出始めたところの雑草であれば根っこも浅く草取り鎌で軽く撫でるだけでも取れます。

一年で草むしりをするには一番タイミングが良い時期は6月
いくら3月頃から春に草むしりをしたとしても、6月の梅雨でたっぷりと水を与えられた草が梅雨の後に一気に成長します。
梅雨が終わって夏になってからでは成長しきっていて大変ですので、その前に草むしりをしてしまいましょう。
梅雨の合間の6月中旬から7月上旬に、夏に成長が始まる雑草を全て叩いてしまいましょう。
梅雨の合間であれば、地面も柔らかくなるので草むしりも楽になります。
6月中旬から7月上旬にしっかりと草取りをしてしまえば、上手く行けば次の春までそれほど気にならない状態に出来る庭もありますね。
ネットが肌に付くと刺されるので、ロンTに虫除けスプレーをしてから着用すれば最強です。
秋に雑草が芽吹いて次の春まで越冬する9月
9月頃も雑草が成長するタイミングです。
9月に草取りをすれば次の3月頃に生える草の量を減らすこともできます。
1年生の雑草や多年生の雑草など種類は色々とあります、9月にもしておくと次の春までは雑草の無い庭で過ごせますね。
草むしりの時期は1年生と多年生の2種類に合わせてする
草むしりの時期やタイミングを知る為には、まず草には1年生と多年生の2種類があることを理解しましょう。
草むしりは1年生と多年生でどの時期に作業をするかを考えれば余計な手間も省くことができますね。
3月頃と9月頃に成長する一年生雑草
1年生の草には大きく分けて2回成長するタイミングがあります。
●3月頃に発芽して秋に枯れる草。
●9月頃に発芽して冬を越して春に枯れる草。
どちらも3月頃や9月頃に発芽して成長しますので、3月と9月は草むしりのタイミングということになります。
伸び始めるタイミングで根こそぎ取ってしまえば次の時期まではたくさん増えることを防ぐことができますね。
1年中いつでも生える多年生雑草
多年生の雑草は1年中いつでも成長するのでやっかいな草です。
雑草で困っているお庭などに生えているのは多くが多年生の雑草です。
どれだけ草むしりを頑張っても、抜いても抜いても生えてくる困った存在ですね。
多年生の雑草は表面が枯れていても根っこさえ残っていれば同じ場所から生え続けるので、冬に枯れても春にはキッチリと生えてきます。
多年草代表のドクダミは駆除しても抜いても生えてくる
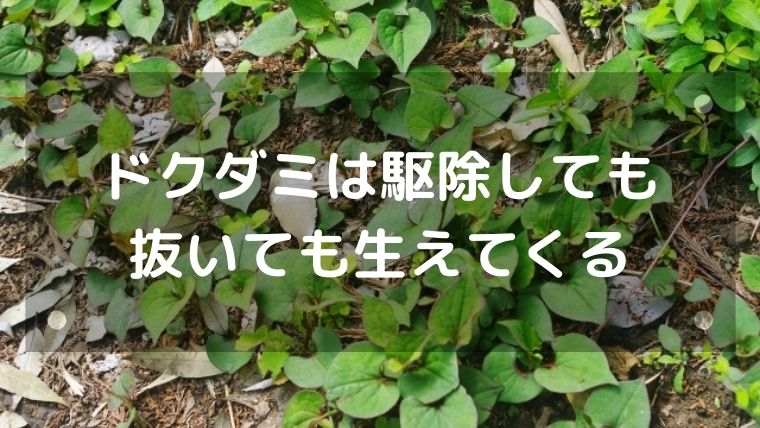
例えば、家の庭にはびこっている多年草で困ることが多いのがドクダミです。
ドクダミの成長するタイミングは3月から11月なので、ほぼ1年中ドクダミを見ることになります。
草むしりでドクダミを抜いたとしても、地面の下で40cmに達する地下茎が生き残っている限りどんどんと広がって増えてきますね。
ドクダミを抜くのであればやはり6月中旬から7月上旬に可能な限り地下茎から抜けば翌年までは比較的マシな状態で過ごせるといったところです。
本気でドクダミを駆除したいのであれば40cmまで掘り下げて徹底的に根を取り除く。
または、地下茎も枯らしてくれるグリホサート系の除草剤で駆除するしかありません。
グリホサート系のサンフーロンは超有名なラウンドアップのジェネリックなので効果は同じなのにお安く買えます。
花壇の中とかでなければある程度駆除してから防草シートと砂利敷きをするのが一番効果がありますね。
ちなみに、ドクダミに熱湯を掛けるのは表面だけ枯らすのにお手軽で良いです。
しかし、後に草花や植木を植えたい場合は土壌の細菌にも影響を与えるのでおすすめできません。
塩をかければ効果はありますが、蓄積すれば今後半永久的に草木が生えない状態になる可能性もあり、流出すれば他の庭木に影響を与えます。
合わせて読んでみる
→庭の雑草対策には防草シートと人工芝を敷くのが簡単・ちょっと高い
多年生のスギナが生える庭はほぼスギナしかない
ドクダミと同じくスギナも多年生の草で庭にはびこって困る種類の一つです。
しかし、ドクダミと違ってスギナが生える庭はスギナが圧倒的に多いですね。
スギナばかり生える理由としては、スギナはスギナよりも背丈が高い草花があると競争力が弱いのであまり生えてこないからです。
また、スギナも地下茎で増えるので草むしりで抜いても抜いても生えてきます。
特にスギナの場合は地下茎が深いと1m以上に達することもあるようなので、根まで抜いたつもりが全く抜けてなかったりもします。
ドクダミと同じく、本気で駆除したいのであればグリホサート系の除草剤で枯らしたところに、下処理をして防草シートと砂利敷きをするのがオススメですね。
草むしりのタイミングまとめ
基本的には、草むしりのタイミングは生え始めて小さい時に取り除くというのが鉄則です。
夏に地面が固くなってガッチリと根付いてしまってからでは取るのが大変です。
草むしりをしても根が土の中に残ってしまうので、夏の太陽の日差しを浴びて草むしりをした矢先に生えてきますね。
ただ、年間に3回もやってられないということであればおすすめのタイミングは・・・
6月終わり頃→3月頃→9月頃の順におすすめのタイミング
自分で草むしりをするのが面倒であれば、くらしのマーケット![]() で地域にある業者の料金や口コミ評価をチェックして依頼するのがおすすめですね。
で地域にある業者の料金や口コミ評価をチェックして依頼するのがおすすめですね。
私が植木屋として働いていた時も、草むしりや草刈りは一度依頼するとずっとリピートしてくれるお客さんが多かったですよ。